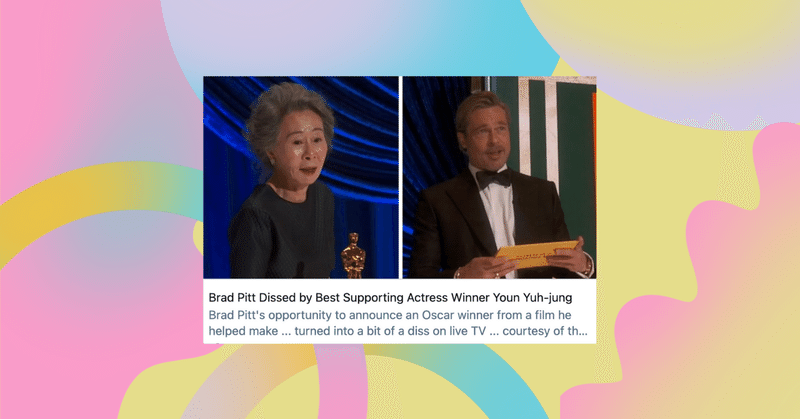
2021年アカデミー賞を振り返る
マジでTLが混乱してる。
— 竹田ダニエル (new) (@daniel_takedaa) April 26, 2021
「授賞式に参加もしてないアンソニーホプキンスが主演男優賞受賞、史上初の3人の有色人種がノミネートされていて、誰もがChadwickに行くと思ってた。少なくともRizかStevenになると思ってたのに?もしかしてみんな怒るの知ってて最後に発表を回したのか??」 https://t.co/PoY0igsTKN
今年度のアカデミー賞で最も話題になった「事故」といえば、作品賞と主演俳優賞の発表順番を入れ替えたにも関わらず、視聴者としては「拍子抜け」の結果となったことだ。この件については詳しく言及している記事が多く存在するので、そちらを参照してほしい。
「ミナリ」の作品賞ノミネートやSteven Yeun(韓国系)、Riz Ahmed(パキスタン系)の主演俳優賞ノミネート、「ノマドランド」監督のChloé Zhao(中国系)の監督賞受賞、H.E.R.(フィリピン系)の「Fight for You」の歌曲賞受賞など、アジア系に対するヘイトクライムがアメリカでも大きな話題になっている中、アジア系の活躍がこれまで以上に評価され、注目されていることは大きな進歩だと感じられた。
中でも議論を呼んだのが、助演女優賞を受賞した韓国のユン・ヨジョンさんのスピーチだ。
アジア系の間でウケたのが、ユン・ヨジョンさんのがスピーチで「西洋人は私の名前を間違って発音しますが、今日は特別に許してあげます」って言った部分 https://t.co/YBwPK4klV9
— 竹田ダニエル (new) (@daniel_takedaa) April 26, 2021
「ご存じのように、私は韓国から来ました。実は私の名前はヨジョン・ユンです。ほとんどのヨーロッパの人々は私をユ・ヨンと呼んだり、中にはユ・ジョンと呼ぶ人もいます。でも、今夜はみなさんのことを許してあげます。」
なぜこの発言がアジア系アメリカ人の間で絶賛されているのか?
そもそも「西洋人の名前ではない」という理由で発音を間違えるのは、非常に失礼で不名誉(かつマイクロアグレッション)だとアメリカではされているのだ。もちろん知識のない状態で間違えてしまうのは仕方がないが、本人によって訂正されたり、著名な人に対して(さらには授賞式という重要な場において)間違えるのは、敬意と文化の尊重に欠けているとみなされるのだ。だから、見ている人も代弁されたかのように「よく言った」と思ってる。
トランプ元大統領がカマラ・ハリス副大統領の名前の発音を何度も間違えて、わざとその「変わった名前」を嘲笑する発言をくり返したことをみて、個人的に傷ついたり、怒りを覚えた人が多い。
「外国人の名前をアメリカ風にアレンジすることは、もちろん可能です。例えば、スペイン語の名前のトリルやロール、アラビア語の特定の文字を発音するのが難しいと感じる人もいるでしょう。私はアメリカ中西部で育ちましたが、私のアメリカ訛りはわずかに音調を変化させ、ガーナ人の親戚と私の名前の発音が異なることを意味します。
しかし、これは人が私の名前をからかったり、馬鹿にしたり、あるいは意図的に間違った発音をすることとは違います。発音の間違いを武器のように使って、私を侮辱しようとする人もいます。私の名前を間違えた人の中には、すぐに次の行動に移る人もいますが、その人はこう言います。"私はあなたをナナと呼ぶわ。それは私がおばあちゃんを呼ぶときの名前です!」と言い返します。
これらの誹謗中傷は、サンスクリット語で蓮を意味するファーストネームを持ち、主要政党の国内チケットでは初の混血女性であるカマラ・デヴィ・ハリスよりも、トランプ氏やパーデュー氏などの不安感や洗練されていない様子を物語っています。
名前を大切にすることは、その人のアイデンティティを尊重することになります。この基本的な礼儀を守れない人には、私と一切関わらないでいただきたいと思います。」
「名前の発音を間違えることはレイシズムの一種だ」という主張についても、数多くの有名人が声をあげています。
「名前」に対してリスペクトを持つべきだということと同様に、代名詞(Pronoun)の選択についても、本人の意向を尊重すべきだということについても言及したい。
さらにこれはアジア系だけの問題ではなく、Boratに出演したマリア・バカローバの名前の発音をブラピが間違えたことでファンが"freak out"したことも話題になった。単に日常生活ではなく、アカデミー賞という映画業界の中でも最高峰の名誉の場において発音を間違えてしまうことの意味を、多くの人が重く感じ取っていることがわかる。
アカデミー賞だけではなく、「ミナリ」をきっかけにさまざまな欧米の授賞式に参加して、ちゃんと名前を覚えてくれないことをアカデミー賞でハッキリと「文句」を言った。これは本当によくある問題で、「アジア人の名前はどうせみんな一緒」とか「西洋の名前じゃないから」という理由で軽視される。
そういうマイクロアグレッションが嫌で、アジアに由来する名前を「西洋化(anglicize)」する人も多い。そして最近のアジア人ヘイトに対するレジスタンスとして、自分の「本名」を用いる人たちも増加している、という記事を紹介する。
また、「ミナリ」の制作費の少なさやブラッド・ピット氏が現場に現れなかったことなど、韓国国内では大女優として尊敬されているユンさんだからこそできる発言も多く報道された。彼女は白人中心の業界構造に媚びなくても韓国国内でキャリアを築き、アジア人のリアルな体験を当事者の視点で当事者によって演じた「ミナリ」という作品で評価された。「愛国主義的」でもなく、名誉白人的でもなく、ただ自尊心を守る「マイノリティ」の姿がここまで力強く感じられたことは、多くのアジア系アメリカ人や移民たちにとって大きな希望と衝撃となった。
ブラピのことばっかり聞いてくるアメリカメディアをシャンパン片手にディスるアジア人のお婆ちゃんがアカデミー賞受賞者なんて、いよいよハリウッドの白人至上主義も衝撃的な速度で崩れてきてるな https://t.co/UJsBIptv06
— 竹田ダニエル (new) (@daniel_takedaa) April 27, 2021
しばらく前だったら、名誉ある場にアジア人が偉そうにして失礼だ!とか言われただろうけど、今では業界の差別や社会の中での偏見や抑圧について視聴者もよくわかっているので、”yes queen言っちゃえ”みたいな反応がほとんどなのも感慨深い
— 竹田ダニエル (new) (@daniel_takedaa) April 27, 2021
今まで「いないこと」にされていたマイノリティが声をあげ、連携をし、カルチャーやメディアの中でも存在感を表していくことで、さらに同胞のrepresentationが増える。それによってエンパワーされた人々が学びを通してさらにさまざまな業界に進出することが可能になる。あくまでも理想的な構造ではあるが、短絡的にいえばメディアが映す「あり方」によって、個人の「あり方」も変わってくるのだ。映画業界でアジア系の活躍が一般的になることによって、業界に蔓延る差別や偏見、そしてそれが映し出す社会の問題や向き合う課題が浮き彫りになる。多様性を尊重したり、人種問題に言及することは「新たな問題を生み出す」ことでは決してなく、今までずっと存在していた問題と向き合う、ただそれだけの過程なのだ。
記事を読んでくださりありがとうございます!いただけたサポートは、記事を書く際に参考しているNew York TimesやLA Times等の十数社のサブスクリプション費用にあてます。

