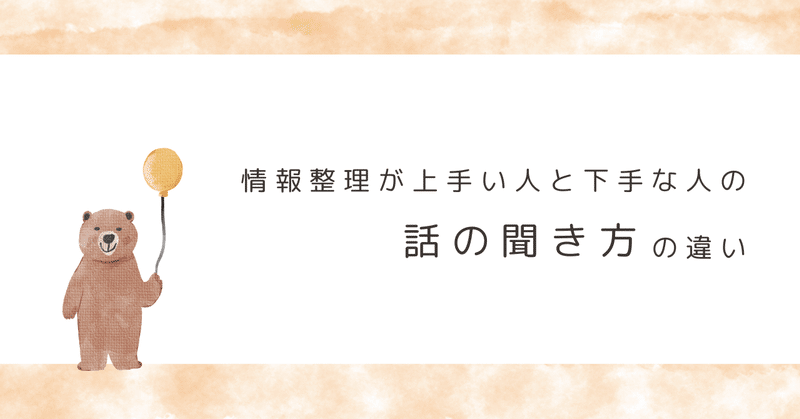
情報整理が上手い人と下手な人の、「話の聞き方」の違い
多くの人が苦手なのは「ロジカルシンキング」ではなく「情報の整理」
「ロジカルシンキングが苦手です」。「言語化が得意ではありません」。そういう悩みを良く聞くのですが、私自身は仕事をしていて、ロジカルシンキングや言語化の能力が必要だと感じる場面はそう多くありません。契約書をまとめるときや、企画や戦略を考えるとき、それらを交渉やプレゼンの場で誰かに伝えるときぐらいでしょうか。
私は新規事業開発の仕事をしているので、そういう機会が人よりは多いと思います。しかし、それでも年中やっているわけではなく、その他大半の時間は部下や上司、同僚やビジネスパートナーとの日々のコミュニケーションに当てられています。そこでは、ロジカルシンキングや言語化力というより、「共感力」や「相手の立場を想像する力」などが主に求められるでしょう。
よく考えると、必要とされるシーンがそれほど頻繁に登場するわけでもないのに、かくも多くの人が苦手だと感じている「ロジカルシンキング」や「言語化力」とは一体何なのだろう。かねてからそう考えていた私は、ある日仕事外の相談者との一対一の面談で、その人のとっていたメモを見てふと気づきました。多くの人が苦手だと言っているのは、「ロジカルシンキング」や「言語化」などではなく、それ以前の「情報の整理」なのではないかと。
誰かから話を聞いたり、誰かの書いた文章を読んだりして仕入れた情報を、うまく頭の中で整理すること。それができないと、そもそも相手の話をよく理解できません。すると、その不理解や誤解を元に考えた自分のアイデアは、当然相手には刺さらないのです。もっと悪い場合は理解すらしてもらえません。このとき、多くの人は理路整然と考えたり、考えたことをわかりやすく伝えるプロセスに問題があると感じるのですが、実は問題はそれより以前に起きているのです。
「お爺さんが」「山に」「芝刈りに」は全く重要な情報ではない
そう気づいて色々な人を観察してみると、情報の整理があまり上手ではないと感じる人の話の「聞き方」に、私はある特徴を発見しました。それは、その人のとっているメモを見せてもらうとよくわかりました。
まず面白かったのが、私の個人的な観察範囲では、必死にメモをとる人ほど情報の整理がうまくない傾向があったことでした。もちろん例外もいますし、実際にはメモを取る・取らないではなく取り方の問題なのですが、情報の整理が苦手なのかなと感じる人の中には、一生懸命メモを取る人が顕著に多かったのです。そして、そのメモの取り方には以下のような特徴がありました。
・とにかく話を聞く
・重要そうなワードやフレーズをメモする
・重要そうなワードやフレーズをメモする
・重要そうなワードやフレーズをメモする
・最後に一見重要そうなワードやフレーズの一覧ができる
この聞き方の何が一体問題なのでしょうか。それは、話を聞き終わった後に話の全体像をうまく組み立てることができない、ということです。話の全体構造がよくわからない状態で、何となく重要そうなところをピックアップしたメモは、それを繋ぎ合わせたところで話の全体構造にはなりません。すると、話を聞き終わった後では、話の全体構造を組み立てるヒントはもうどこにも残っていない、ということになってしまうのです。
例えば、桃太郎の話の全体構造を理解している私たちは、「お婆さんが川に洗濯に行った」というくだりが物語の鍵を握る重要な情報だと知っています。逆に「お爺さんが山に芝刈りに行った」というのは、言ってみればどうでもいい情報です。なので、「お爺さんが」「山に」行ったのか!それも何と「芝刈りに」行ったのか!と、そこを掘り下げて必死にメモしても、後で見返して意味のあるものにはなりません。話の整理が苦手な人は、極端な話をすればこういう話の聞き方をしているのです。
仮説としての話の全体構造を、話を聞きながら磨いていく
しかし、桃太郎の物語を生まれて初めて聞く子供には、話の全体像などわかるよしもありません。そして、それは仕事で誰かの話を聞いたり、誰かの書いた文章を読む私たちも一緒でしょう。そんななか、情報の整理が上手な人は、一体どのように人の話を聞いているのでしょうか。その鍵は「仮説」にあります。そういう人は、以下のように話を聞いていると私は考えるのです。
・まず仮説として話の全体構造を思い描く
・仮説を証明/反証するための情報を話の中から探す
・その情報を元に仮説を微調整する
・それをさらに証明/反証するための情報を話の中から探す
このようなスタンスで話を聞いていると、話を聞き終えた時点で、話の全体像が自然と頭の中に出来上がっています。もう少し正確に言うと、話の全体像に関する、磨きのかかった、精度の高い仮説が自然と出来上がっているのです。この状態で話を頭の中に入れておくと、正確に覚えておきたい数字や固有名詞だけをサッとメモしておく程度でも、後で話の幹や枝葉を引き出すことができるようになります。頭の中に葉っぱがバラバラに散らばっているのではなく、この木のこの枝にこの葉っぱ、という整理整頓ができた状態で情報を格納できるからです。
ロジカルシンキングは一旦忘れて、話の聞き方を変えてみる
このような「聞き方」ができるようになるには、ある程度の慣れが必要でしょう。その上で何より重要なのは、まず「仮説検証モード」に話の聞き方を思い切って切り替えるてしまうことです。はじめはうまくできず、頭に入ってくる情報がよりごちゃごちゃになってしまうリスクもありますが、それでも切り替えてみないことには何も始まりません。
そうしないと、いつまで経っても必要な訓練ができず、一向に情報の整理がうまくならないのです。うまくいかずに焦って必死にメモをとるようになり、それでもうまくいかないのでさらに必死にメモをとるようになる。そんな悪循環が生まれてしまいます。何を隠そう、これが私の、必死にメモをとる人ほど情報の整理がうまくない、という傾向に対する仮説です。
ひとたびこうして話の内容をより正確に理解することができ、それを頭の中にうまく保存しておくことができ、さらにそれをうまく取り出すことができるようになれば。たとえ「ロジカルに考える」ことができなくても、巧みに言葉を操って「言語化」できなくても、仕事におけるコミュニケーションはぐっと円滑になることが想像できるのではないでしょうか。
むしろ、それができるようになった皆さんを、周りの人はこう評価するようになるかもしれません。あの人はロジカルシンキングができる、あの人は言語化がうまい、と。そんな自分の姿までが何となく想像できるのであれば、まずは「ロジカルシンキング」のことは一旦忘れてみてはどうでしょうか。そして、話の聞き方を変えることにトライしてみてはどうでしょうか。
おわり
<新刊発売>
Noteが気に入ったら、ぜひ書籍も手に取ってみてください!
幸せな仕事はどこにある: 本当の「やりたいこと」が見つかるハカセのマーケティング講義
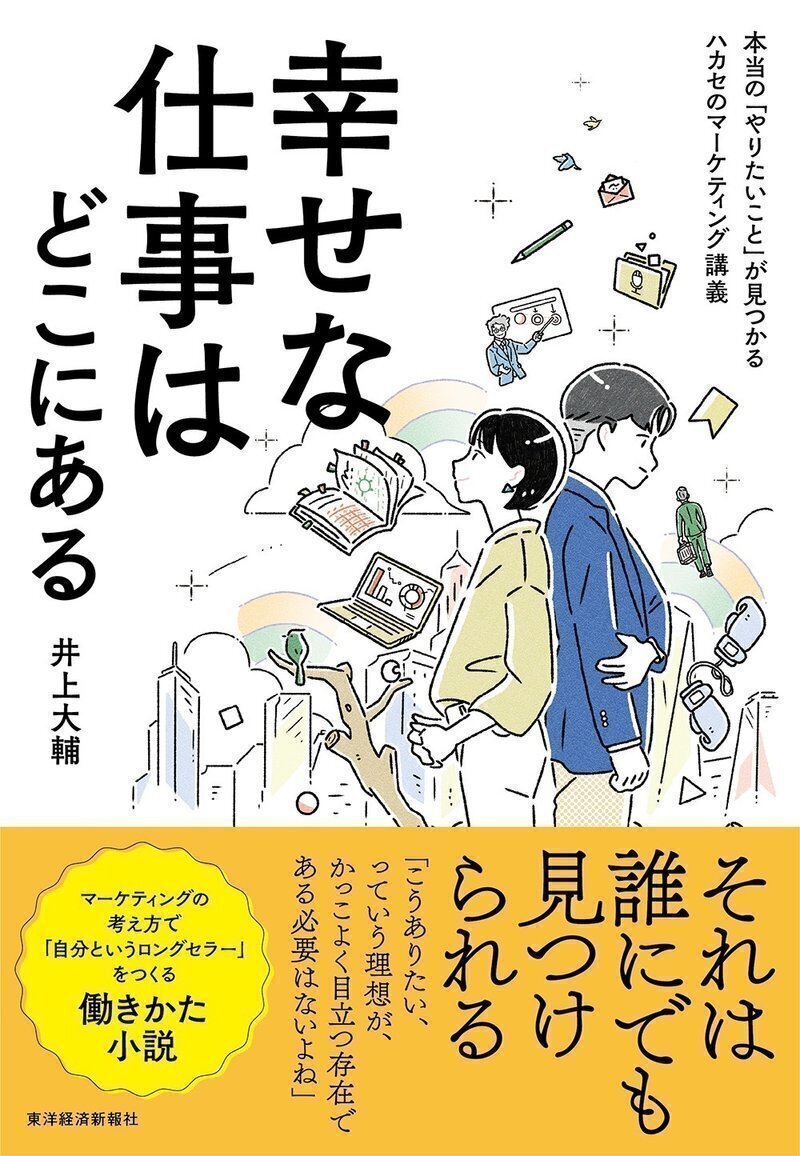
<この本のコンセプト(本書より)>
幸せに働きたい。
月曜日の朝に目が覚めたら、これから始まる1週間にワクワクしているような仕事がしたい。
出世なんてしなくても、有名にならなくてもいいから、本当の「やりたいこと」を見つけ、それを誰にも壊されないような働きかたを見つけたい。
この本はそう思っている人に向けて書きました。
そんな「幸せな仕事」が見つからないのは、「見つけるための方法」を知らないから、かもしれません。
私は、その方法を、自分の個性を磨くことと、誰かの役に立つことを両立させるマーケティングの考え方から学びました。
たとえば個性を磨くことは「差別化」、誰かの役に立つことは「ニーズ」という考え方が、それを教えてくれました。
この本は、ちょっと変わった先生の講義を通じてそんな考え方を学ぶことで、3人の男女がそれぞれの幸せな仕事を見つけるまでの物語を描いた「小説」です。
さあ、ページをめくって物語の世界に飛び込んでみてください。
それが「幸せな仕事」を見つけるはじめの一歩です。
幸せな仕事はどこにある: 本当の「やりたいこと」が見つかるハカセのマーケティング講義
#COMEMO
#NIKKEI
<より考えを深めるために読みたい記事>
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD143Y70U3A710C2000000/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

