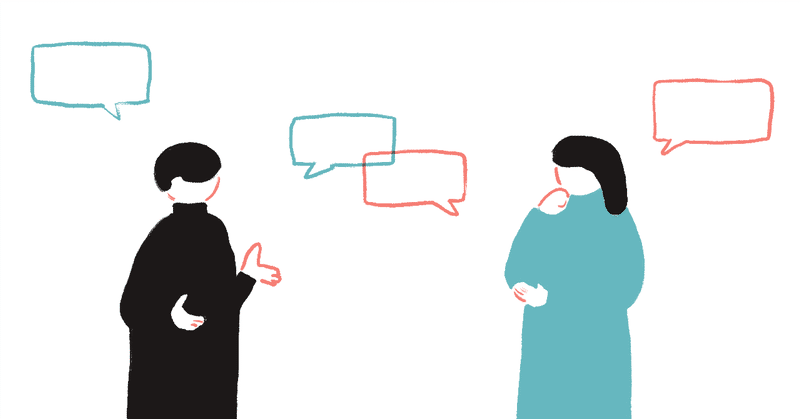
「言語-化」とは、世界を再構成し続ける動的な「運動」である
お疲れさまです、メタバースクリエイターズ若宮です。
今日は「言語化」というテーマについて書いてみたいと思います。
言語は世界を認識・構成するもの
僕はけっこう言語とか言葉が好きなのですが、大学で美学芸術学を学んでいた頃、言語学とか構造主義とか記号論(ソシュールとかヤコブソンとかバルトとか)あたりも少しかじっていました。
言語論ではソシュールを嚆矢として、所謂「言語論的転回」とも呼ばれる極めて重要なパラダイムシフトがありました。
「言語論的転回」の元ネタは「コペルニクス的転回」です。コペルニクスが地球中心の地動説から天動説へと世界の見え方を大転換したのにひっかけてカントが言った言葉です。
カントは、世界が既に存在し、我々人間がそれを受け取るという従来の素朴な認識論を逆転させて、世界を受動的に受け取るのではなく、われわれ自身が認識によって世界を構成している、という主体の転換を提示しました。
「言語論的転回」もこれと似ています。それまでの言語論では、物事や事象が既に存在しており、それに対応する言葉が当てられるのだ、と考えられていました。しかし、ソシュールはこれをひっくり返し、人は言葉と、他の言葉との相関的な構造によって知ることによって初めて世界を認識でき、現実は言葉があってはじめて構成されることができる、という考えを示したわけです。
言語が現実を構成するという考え方は、言語を事物のラベルのように見なす西洋哲学の伝統や常識の主流に反していた。たとえば、ここで言う伝統的な考え方では、まず最初に、実際のいすのようなものがあると思われ、それに続いて「いす」という言葉が参照するいすという意味があると考える。しかし、「いす」と「いす」以外の言葉(「つくえ」でも何でもいい)との差異を知らなければ、私たちは、いすがいすであると認識できないだろう。以上のようにフェルディナン・ド・ソシュールによれば、言語の意味は音声的差異から独立しては存在しえず、意味の差異は私たちの知覚を構造化していると言う。したがって、私たちが現実に関して知ることができることすべては、言語によって条件づけられているというのである。
つまり言葉は後付けの単なるラベルではなく、世界を認識し構築するいわば基盤です。
言語がもつ意味やニュアンスは、僕らが世界認識を大いに左右します。言葉によって、僕らの世界そのものが広がり、深まり、そして変化するのです。
虹の色は言語によってちがう
構造主義とか言語学とかいうと抽象的でわかりづらいですが、具体的にいうと、たとえばよくあげられる「虹の色」があります。
僕らは普通「虹は七いろ」と考えていますよね。しかし、この「7つ」というのは言語によって生まれる区別でしかなく、言語が変わればその認識は変わってしまいます。かつて日本では五色だったと言いますし、二色しか区分がない民族もあるそうです。
本来、色というのはスペクトラムのように連続的に変化しているもので、その分け方は暫定的・恣意的なものでしかなく、やろうと思えば無限に分けて行くことも可能です。(実際、500色の色鉛筆だってあります)
そしてその分節は、文化や言語によって変わるのです。
虹は7色、というのがスタンダードだと思っている人達からすると、3色しか認識していない人に対して「本当は7色なのだけど数えられていないのだな」というように思うかもしれませんが、そうではありません。僕らには7色に見えているように、3色しか言葉を持たない人にとっては、実際に虹は3色のものとして認識・体験されているというところがポイントです。
これは色以外でも同じです。例えば、英語ではお米は「rice」ですが、日本語では「稲」「ご飯」など色々な呼び方があります。主食が米だから言葉がたくさんあり、それによって細かく認識できるのです。
また、エスキモーの人たちは雪を物凄いたくさんの言葉で表現します。その言葉や概念を持たない人からすると、雪は等しく「雪」でしかありません。
それぞれの言語によってそれぞれ異なるピクセルで、現実はマトリックスの世界のように構成されるのです。
だからこそ言葉は、僕らに世界を認識させてくれ、豊かにするツールだとも言えます。言葉をたくさん知っているということは、それだけ解像度が高く世界を認識できるということです。
例えば、ワインのソムリエはワインの風味を表す言葉をたくさん持っていて、それだけワインをより豊かに味わうことができます。
しかし、言語を超えたものも常にある
すでに述べたように、言語は世界を認識し構成するための素子です。
ソムリエの事例のように、アートや味覚などを味わうとする時にも、言語が体験を豊かにしてくれます。感性的な領域の話になると、よく「言葉にせず、虚心坦懐にただ味わうべきなのであーる!」ということが言われたりしますが、僕はそうは思いません。
なぜなら「感性」というのは感覚刺激そのものではなく、その面白さを味わうためには文化的コンテキストや意味づけが必要だからです。アートには、絵の見方や世界の捉え方の面白さがあります。たとえば茶の湯がそうですが、香りや料理を味わうことも純粋な感覚ではなく、知的な楽しみです。
なので、たとえ感性的なことでもそれを豊かに味わう上で言語化というのは重要です。
しかしその上で、言語にはどうしても捉えられないゾーンも存在すると常に意識することも大切だと思います。言語の重要性を知りつつ、言語の限界も理解する。
例えば、「リンゴは赤い」と言った時、厳密にはそのリンゴの赤さは微妙に違い、同じリンゴでも見ている人や方向によって光の加減で全然違う色を見ているわけですよね。しかし「りんごは赤い」と言う時、言葉で色の感覚が十全に共有できた、と勘違いしてしまう。
言語は「ここからここまでは赤ということにしましょう」というような、恣意的な単位の切り出しないしラベリングなので、ある種デジタルな側面があり、アナログな体験や色の深みを捉え損ねてしまうこともあります。
言語は世界の認識に役立つものですが、素子の解像度としてはざっくりしている。言語がすべてだと思ってしまうと、さらに深いアナログな体験の味わいができなくなってしまうかもしれません。言語化は大事ですが言語化してすべて尽きるわけではなく、その先に常に言語化できないゾーンがあることを同時に意識することが大事だと思っています。
人間が世界を認識したりそれを伝え合うには言語が欠かせない一方で、言語には常に及ばない部分もある、というのは原罪的なジレンマです。その葛藤とともにあることが、言語化という行為なのです。
without words ではなく beyond words
アートやアート思考でも、「言葉にできない」ところがあるのは間違いありません。しかし、その一方で、「言葉にしない」と言語化を放棄するのは、アートや文化の面白さに向き合う努力を放棄してしまうことと同義です。
大切なのは、言葉を用いないことではなく、言葉を使いつつもその先に想像力を働かせることです。「without words」ではなく「beyond words」、「without description」ではな「beyond description」です。
言葉を用いて世界を再構成し、言語化により認識を深めた上で、さらにそれを超える領域に漸進的かつ極限的に迫ろうとすること。
僕は美学や芸術学という学問を通じて、言葉にできないものをできるだけ言葉にする訓練をある程度してきました。いまでは割と言語化能力が高いと褒めていただくことがありますが、それはその訓練の結果です。言語化の力を磨くにはアートや感覚的なものをできるだけ言語化する訓練をおすすめだと思います。
そして、言葉にならないことを言葉にする努力は、詩的poeticな言葉の使用を必要とします。
詩の言葉は、論理的な散文の言語とは異なり、比喩やオノマトペ、韻や語呂合わせなどを使ってジャンプするようなところがあります。「茶色い戦争がありました」という中原中也の詩は、文字通り茶色い軍服を来た人同士で戦闘が繰り広げられているという意味ではなく、独特の質をもって僕らに語りかけてきます。和歌を味わうのは、論理的な言語で意味を解説することとはちがいます。
僕も、言語化する際に比喩をすごく使います。これは感性の領域のことだけでなかう、事業や経営についてもたとえば「事業は生き物である」というような比喩をしたり、事業のライフサイクルを人間の一生に例えたりします。すると「今、これは赤ちゃんの段階だから、身長や年収より大切なことがあるな」というように、比喩からの逆照射によって、物事の理解が深まります。
言葉にならない領域に進むときには、比喩など字義通りの言葉の使用を超えて語らざるを得ない。言葉が詩的poeticになる時が「本当の意味での言語化」だと僕は思います。
本当の意味での「言語-化」は、ことばにならないものをことばにする運動
「本当の意味での言語化」という言い方をしました。「言語-化」とは厳密にいうと、「まだ言語ではないものを言語にすること」です。例えば、「リンゴ」という言葉でリンゴを指し示す時、それは既に名前があるものを言葉で置き換えているだけですよね。この場合、僕らは言語を単に使っているだけで、新たに言語を生み出す「言語-化」をしているわけではありません。
「言語-化」とは動的な「運動」なのです。
この「運動」の感覚を失うと、認識や表現が型にはまったものになり、想像力が停滞してしまいます。例えば、「リンゴは赤い」と言う時、その「赤」の深さまで思い至ることなく、記号的理解で思考が停止してしまう。それは、本当の意味での「言語-化」ができていないということだと思います。
そして、「言語-化」の運動は継続的でなければなりません。
「死んだメタファー」ということばがあります。これは、当初はポエティックな力をもつ「言語-化」表現だったものが、次第に紋切り型の表現になってしまうことを指します。比喩やメタファーというものは、時間が経つと「死んで」しまうのです。(たとえば「机の脚」ということばを聞いて、メタファーや詩的な表現だと感じることはあまりありません)
そもそも、メタファーというのは字義通りには「正しく」ないこともあります。「人間は狼だ」という表現は、字義通りには誤りです。しかしその誤りによって、そこには既に了解された語義を超えて、新たな意味がたち現れます。「人間は狼だ」という表現は、それを聞いた人のうちに人間と狼との共通点を探索する運動を生じさせます。これが「言語-化の運動」です。しかし、時間が経ちその表現も馴れてしまうと、徐々にこの運動は起こらなくなり、思考が停止し「死んだメタファー」になってしまうんですよね。
「言語-化」というのは、死んだメタファーから再び新しいメタファーを生み出す不断の更新作業でもあります。その運動によって新しい表現が生まれ、新しい世界の見方が生まれます。言葉を新しく作り出す、それこそが人間の言語の素晴らしい能力ではないでしょうか。
アート思考な経営者の代表とも言える遠山さんはこんなことをおっしゃっています
世の中に存在したり、言語化されたりしているのはまだ10%程度にすぎない。「残りの90%は闇の中にある」と思ってきた。だから「世の中に存在しないものを自分たちの手で生み出していく」。その不断の試みがスマイルズの存在価値だと考えている。
未知への探索にあたって頼ってきたのが言葉の力だ。遠山さんは「表現の名手」と形容したくなるほどに、ユニークな言葉を編み出しては未来に向かう推進力にしてきた。
言語を軽視するのではなく、言語を用いて世界を構成することができるという能力は、人間の定義といえるほどに重要な能力です。
ただし、言葉は表面的な記号になってしまう罠もあります。属性でのレッテル貼りなんかもそうですが、言葉があることで体験の細かな差異を捨象し、わかったつもりになってしまう。言語化できないものが常に存在すると認識することが重要です。
そしてその言葉にならない部分をどうにかして言葉にするという運動こそ「言語-化」であり、それはしばしば詩的poeticな言葉になるのです。
しかし詩的な言語も、やがてはメタファーとして死んでしまいます。これ自体は悪いことではなく、肌の角質化のようなもので固くなることで体を守る「殻」になります。フレームワークや概念の枠組みのようにそれは便利ですが、思考停止や経路依存を生みます。ニーチェは
脱皮できない蛇は滅びる。意見を脱皮することを妨げられた精神も同様だ。それは精神ではなくなる
と言っています。
言語化の先にあるものを新たに言葉にしようとする努力、「言語-化」の本質とはそうした「絶え間ない動的な運動」ではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

