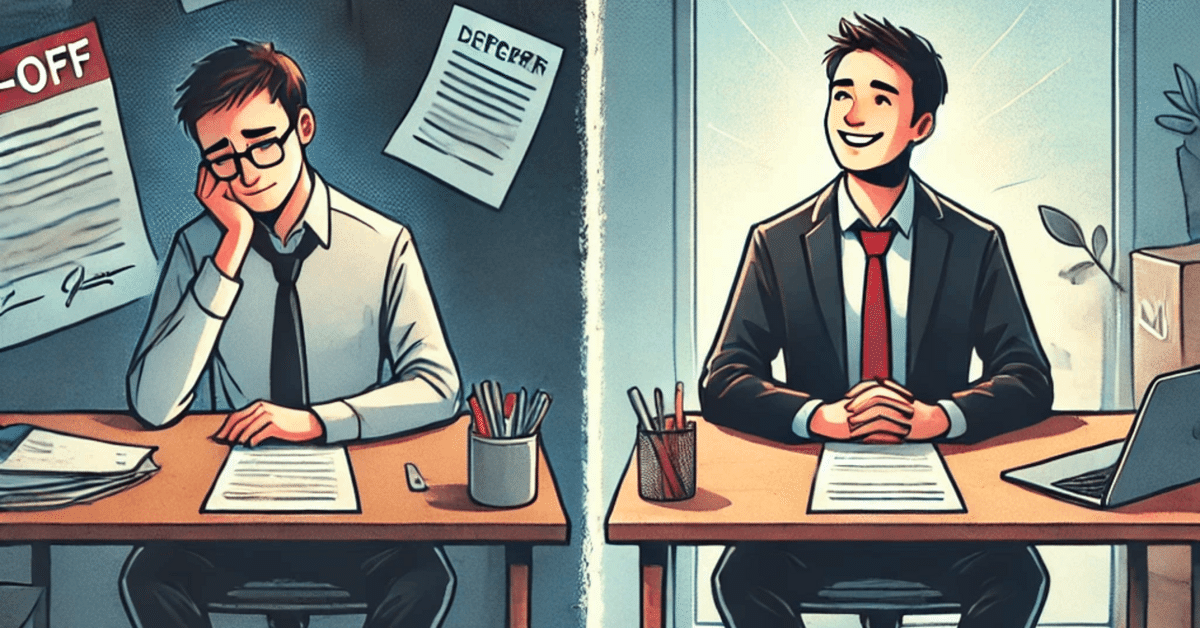
レイオフは終わりじゃない アメリカ人はこうしてキャリアを築く
イーロン・マスク率いる米政府効率化省(DOGE)が本格的に動き出した。連邦政府職員の新規採用を停止し、テレワークを禁止。職員に対し、テレワーク禁止などの管理強化に従うか、早期退職に応じるかを迫り、すでに全職員の3%程度の約6万人が早期退職に応募したらしい。今後さらなるレイオフも断行されるのだろう。
いきなり働き方のルールを変えて、それに従わない者には強制的に退職を迫る。さらにレイオフする。とんでもなく強引で冷酷な仕打ち。アメリカ国内でも実際に大きな問題として騒がれている。だが、よく似たことはアメリカの企業では日常茶飯事で起きている。アメリカ社会・企業が流動性と経済合理性を重視するためだ。
アメリカの企業は、その時その時の自社内の状況に応じて、外部環境に応じて、ストラテジーをコロコロ変容させる。ある時は、既存のプロジェクトを加速させる。新規プロジェクトを稼働させる。仕事が一気に増え、人が足らなくなる。そうかと思えば、たくさんのプロジェクトを突然中止する。急に人が余る。人が余った時、経済合理性を重視すれば、「雇用を守り、余った人員も何とか抱えておこう」とはならない。余ればレイオフする。足りなくなったら、また新たな人材を雇えばいい。大企業でも、数年ごとにリクルートと、大規模なレイオフを繰り返す。社員の雇用を守るという日本の会社のような温かみはない。冷酷だ。ただ、皮肉にも、そんな流動性と経済合理性を徹底するアジャイル型経営がアメリカ企業を強くしている。
自分が転職したせいで、同僚がレイオフに追い込まれたケースを二度経験した。二つの異なる会社での経験だが、パターンは同じだった。パフォーマンスに問題がある訳では全くなく、ただ、タイミングの問題で同僚はレイオフの犠牲者となった。同僚は1年ほど早く転職していた。1年後に僕が転職し新たに加わった。会社はプロジェクトが増えて、拡張期にあった。転職者がいっぱい入り、社員数が急増した時期だった。しかし、僕が入って数か月後、状況が一転した。急にたくさんのプロジェクトが中止となり、縮小期に転じた。少し前まで、人員不足で新たな転職者を入れ続ける拡張期にあったのに、今度は人余り状態になってしまった。レイオフが断行される時が来た。二度とも、僕は転職に伴って大きな引越しをした。会社はリロケーションサポートとして僕の引越に関わる費用まで負担した。会社にとって、わざわざ引越させ、その費用まで負担した上、転職後数か月しか経っていない社員をレイオフすることはできない。あまりにも愚かな行為だ。僕は転職した時期が余りにも間近だったためレイオフの対象から外れた。代わりに転職後1年以上経過していた同僚が犠牲となった。彼らは転職に伴った引越もしておらず、会社にとってはレイオフしやすかった。彼らが被ったレイオフは誰にでも起こり得る。「タイミングガチャ」だけで去る人、残る人が決まるレイオフだった。
ただし、レイオフされた同僚はいつまでも犠牲者としてうなだれていた訳ではない。まもなく転職を成功させ、これまで以上のポジションに就いた。レイオフ時には会社からSeverance Packageと呼ばれる数か月分の給料に相当する退職金が支給された。レイオフを告げられ、新たな転職先が決まるまでは、確かに大変だっただろう。特に精神的にはしんどい。でも、彼らの人生全体から見たら、結果的には次元上昇だ。ポジションは上がり、臨時収入も入った。レイオフを告げられ、会社を去る時も、彼らはとてもプロフェッショナルだった。もちろん心のうちは複雑だったはずだ。しかし、感情的になることもなく、最後までしっかり自分の仕事をこなした。同僚ともしっかりあいさつを交わし、これからも繋がっていようと仲間であることを確認し合った。そのようにプロフェッショナルな行動をとることが、ゆくゆく自分にポジティブな結果となって返ってくると身についている。そういうマインドセットが出来上がっている。実際、僕も彼らの新たな転職活動の際、リファレンスチェックで応援することができた。
いつでもレイオフされる可能性のある不安定な雇用。だが、雇われる側も、ただ指をくわえて黙っている訳ではない。いつでもレイオフされ得る状況だからこそ、自立心が発達する。会社は、自己実現のための乗り物に過ぎない。ひとつの乗り物にずっと乗っている必要はない。乗り換え自由だ。「ひとつの職場に長くいる」よりも「キャリアを築く」の意識が強くなる。自分のスキルと市場価値を常に意識する。レイオフされても立ち直れる力を身につける。「レイオフされた=能力が低い」ではないという意識がある。実際、レイオフを経て、よりよいポジションに就くケースも多い。レイオフからの転職は前向きなキャリア形成の一環であり、次元上昇の機会だ。
このような状況だから、雇う企業側も採用の際に、レイオフの事実をネガティブに捉えることはない。当人の能力とは関係のない不可抗力の出来事だ。それどころか失敗や挫折でさえポジティブにとらえてくれる文化がある。レイオフより遥かに厳しい状況で転職活動をせざるを得なくなった経験がある。僕の履歴書には6ヶ月の空白期間がある。僕にとっては大きな挫折だった。上司との人間関係が悪化し、おまけにパフォーマンスも悪く、最低の評価を受け、ほとんどクビ同然で会社を逃げるように去った。急だったため転職活動もしていなかった。その後、半年間、失業期間が続いた。普通に考えたら、会社にとって、パフォーマンスが悪くてクビになった人間を、新たに採用するのは、かなりリスキーだ。しかし、そんな状況でさえ、僕のよいところを見てくれて採用してくれた会社があった。しかも、僕にとって願ってもない会社だった。転職条件も申し分ないものだった。失敗し挫折した人間にも、何度もチャンスが与えられ、やり直す挑戦ができる。それが僕のアメリカが好きな最大の理由だ。
トランプ新政権下で行政機関を追われることになる人たちも同じようなマインドセットを持っているはずだ。実際、僕のいる製薬業界では、製薬会社と行政機関であるFDA (Food and Drug Administration)を行き来した同僚が何人もいる。僕も以前に行政側を経験してみたいと強く思い、その機会を探ったことがある。残念ながら縁がなかったが、新薬を開発する側と、開発された新薬を審査する側の両方を経験できたら、キャリア形成の面で超貴重だ。行政機関を追われて自主退職したり、レイオフされた人たちも、トランプ新政権の被害者だとずっと落ち込んでいる訳ではないだろう。スキルアップと自分の市場価値を意識して生きてきた人間だったら、逆にキャリアアップの好機到来と捉えているはずだ。
日本でも働き方が多様化し、早期退職、レイオフ、その他さまざまな理由で一時的に失職することは多くなるだろう。多くの会社で日本従来のメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へのシフトが起こっている。その際には必ず組織に歪みが生じる。早期退職を強いられたり、さらに強硬なレイオフが行われることも増えるだろう。大企業に入れば、定年まで安泰という時代も終わった。そんな時代だから大企業よりも敢えてスタートアップに挑戦する人材も増えている。それ自体は素晴らしいことだが、スタートアップの数が増えれば、当然、失敗するスタートアップの数も増える。転職する人、一時的にポジションを失う人もたくさん出てくるだろう。
今後、人手不足がさらに加速する日本。転職回数、レイオフ、失職、失敗・挫折の経験を減点方式で採点する終身雇用的価値観の抜けない会社は、生き残っていけなくなるだろう。転職やレイオフだけでなく、実際の失敗・挫折の経験でさえ、マイナス点ではなく、そこから学んだ経験をプラス点として評価する会社が、人的資本を活かして成長していくと思っている。

