
絶対王者がなぜ予選落ちしたか ― まさかそうはならんだろう
絶対王者の瀬戸大也選手が東京五輪水泳男子400mメドレーで予選落ちをした。350mまでトップを泳いでいた。いつものようにバタフライで先行し、後半余力をもって流していたところ、ラスト100mで周りのギアチェンジに追いつけず5着に沈んだ。
各国は事前に研究していた、瀬戸選手が予選の後半でペースをおとすということを。だからそこで一気にスパートをかける作戦をとった。“ダイヤはスタートで先行。そのあと、決勝に向けて体力を温存するためにペースを落とす”というレース分析をして、それを踏まえた作戦を遂行した。瀬戸選手もそれは予想していただろうが、予想外の展開だったのだろう。実力を発揮できず敗退した。翌日の男子200m自由型の予選に出場した有力選手だった松元克央選手も予選落ちした。同じような姿を2日連続で見た。
1.分析されることに弱い日本
日本人は分析に弱い。もっといえば分析されることに弱い。
![]()
と考える。
瀬戸大也選手は予選のその組の5位となった。予想通り、ダイヤは予選の後半にペースダウンした。その時に全力で泳ぐ。気がついたときは、遅かった。レース後、瀬戸大也選手は狐につままれたような顔をしていた。おそらくその時は敗北感がなかっただろう。「油断はしてなかったが、読み違えた」と言った。つまり
![]()
この姿が現代日本社会を象徴している。日本の大学は世界でのランクを一気に落とした。アジア1位の立場からずりおちた。中国の大学に、シンガポールの大学に追い抜かれた。気がつけば中国・東南アジアの大学の方が、日本の大学よりも上になっていた。大学だけではない。産業もエンタメも日本社会のいろいろなところで、このような状況がおこっている。世界の中の日本、アジアの中の日本の立ち位置に気づいていないうちに、その状況が変わった。
これは「ゆでガエル」とはちがう。昔取った杵柄で偉そうにしている「先生」「先輩」という構図ともちがう。「自分が追いつかれている」と気づく感覚が弱くなった。
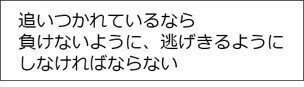
と思わねばならないのに、追いつかれていることに気づかない。なぜか ―― こう考える日本人が多くなった。
![]()
2.「そうはならんだろう」ということづくしの日本
日本のモノづくりはかつて、
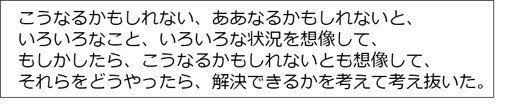
それが、日本のモノづくりの基本であった。モノをつくるときは、“こうじゃないとあかん、ああじゃないとあかん、こうなっちゃあかん”― とお客さまが使われている姿を思い浮かべて、お客さまに喜んでもらえるよう、“ああなる、こうなるかもしれないということ”を事前に潰して、徹底的に精緻にするから、「日本のモノづくりはすごい」といわれた。日本の製品は、なにをやってもすごい、なにがあっても壊れない、といわれた。
それはモノづくりにおいて
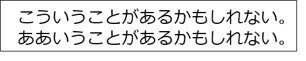
という姿をいっぱい想像して、その可能性を事前につぶしてきた。
それが、いつの間にか、「こうなる、ああなる」を思い浮かべる姿が減り、「そうはならんだろう」と考える人が多くなった。
3.「まさかは起こらない」と思う日本人
20~30年前から、商品の取扱説明書に、
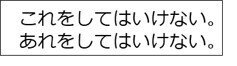
ということが、どっさりと書かれるようになった。“これをやってはいけない。これをしたら、感電します”などと書くようになった。世界ではそういわないと、“それをやってしまう人がいるのだろう”から、書いてあるのだろうと、当初は思った。しかし

その「これをしてはいけない」「あれをしてはいけない」が増えていくのと同時に、お客さまの姿がだんだん見えなくなった。
モノづくりだけではない。モノづくり以外の世界でも、「まさかそうなることはないだろう」ということで、埋めつくされるようになった。
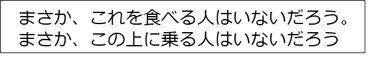
そして、だんだんその「まさか」はおこらないだろうと思うようになった。
だから、なにかコトがおこると、慌てる、焦る。
「こうかもしれない、ああかもしれない」と考える。ところが、それまでに考えていなかったことがおこる。そうすると、想定外とか、まさかそうなるとは思わなかったとか、それまで精緻に物事をうるさくつめていた人が、いきなり論理的、科学的なアプローチをやめて、
![]()
とまるで、超常現象のようにいう。たとえば東日本大震災の時もそう。有事に備えて、時間と人をかけて徹底的につきつめてきた。しかし津波が想定外の高さでやってきた。
![]()
「想定外」という言葉が日本社会に広がったのは、決して大昔のことではない。
瀬戸大也選手やコーチも含めて、若しかしたら、ライバルがそのときにスパートをかけてくると、考えなかったわけではなかっただろう。厳しい練習をしてきて、今季世界1位の記録をたたきだしていた。金メダルを取るために作戦を練ってきただろう。しかしながら瀬戸選手が決勝に備えて予選で力を温存することをライバルたちは事前に分析し、瀬戸チームの想定した以上の作戦がおこなわれたことが、予選でのダイヤおとしとなったのかもしれない― その姿が「現代日本」を象徴しているようにも感じる。

