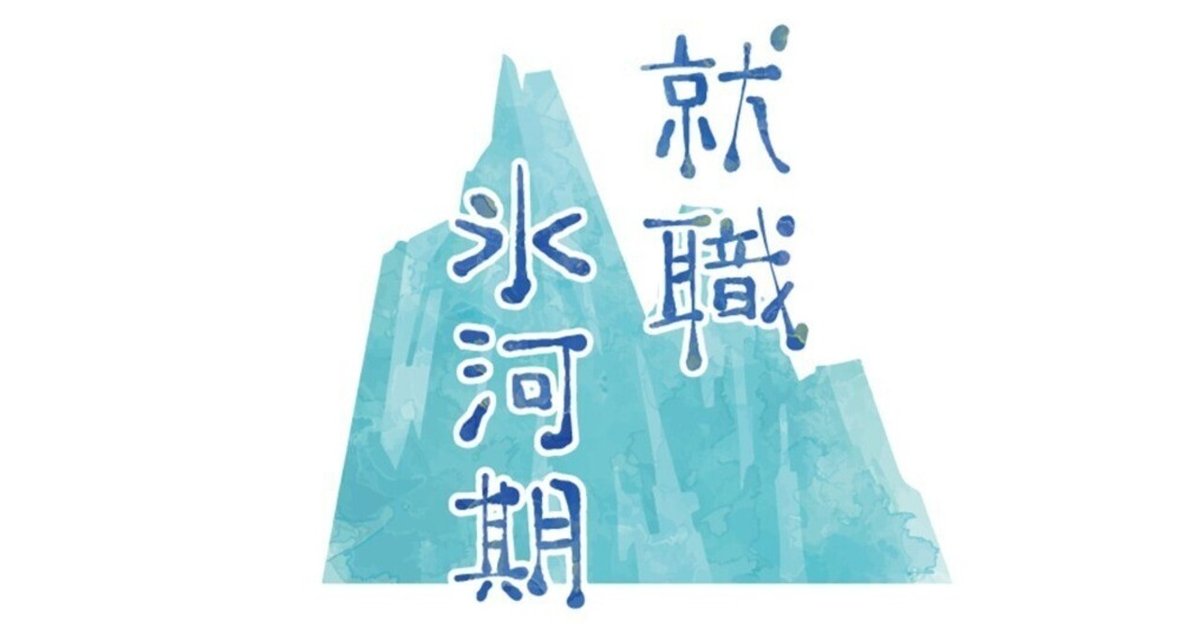
氷河期世代の困難:アメリカとの比較で見える日本の働き方の歪
40~50代の持ち家率が急低下している。全世代平均は横ばいだが、40~50代は30年前と比べ10ポイント前後も下がった。この年代は就職氷河期世代といわれ、就職難に見舞われた。就職氷河期世代はおおむね1993~2004年の間に社会に出た人を指す。全体では2000万人を超え、実に総人口の6分の1となる。現在も経済的な苦境は続いており、老後の年金も多くを望めなければ賃貸に住むこともままならない。「安住の家」を求めてさまよい続けることになる。
僕はバブル末期の1991年に大企業に入った。大学時代遊びほうけていても会社が採用してくれる「よい?」時代だった。採用の際の用紙に小学生で習う漢字も書けなくて、付き添ってくれた同じ大学出身の先輩に「君、漢字知らないな~!」と呆れられた。採用担当の方が「緊張してるだけですよね」と慌ててフォローして下さったのを覚えている。その後すぐにバブルがはじけ、10年も続く就職氷河期世代が来るとは、夢にも思わなかった。
僕が入社した1991年は、会社史上、最も多くの新卒社員が入社した年。同期は200名以上もいた。僕は100名程度の社員のいる部署に配属されたが、そこだけで僕を含め10名の新入社員が入った。ところが翌年はたった1名となった。バブルの影響を受けにくい製薬業界だったが、それでもバブル崩壊の影響はあからさまだった。その後、どこの会社でも行われたさまざまな変革が施行された。ある部署を別会社にして本体から切り離す。正社員を採用する代わりに派遣社員で埋める。働く時間ではなく会社への貢献度で評価する成果主義、裁量労働制を導入してみる。などなど。バブル崩壊後、世界と競っていくための効率化だが、同時に社員の雇用は何としてでも守りたいという日本の会社ならではの苦肉の策でもある。そういう面では、日本の会社は、温かい。家族のようだ。だが、就職氷河期世代のように、会社自体に入れないとなると一転して超冷酷だ。いったんレールを外れると生涯苦しむという構造的な問題となってしまっている。生まれる年が数年違うだけで、恐ろしいほどの不公平感、格差を生む日本の働き方の歪となってしまった。
2003年以降、20年以上アメリカで働いてみて、日本の働き方の歪を強く感じる。アメリカでも2008年のリーマンショック、2020年のコロナ禍の際に、新卒者が就職難に直面した。多くの企業が雇用を控える傾向にあった。特にそれまでに職歴のない新卒者は、自分の希望する職種に就けなかったり、低賃金で契約せざるを得なかった。ただし、終身雇用の概念がないため、新卒一括採用の仕組みがない。そのため、一定の年代だけが長期にわたり社会全体で取り残される構造は少ない。
2021年、僕がスタートアップの製薬会社で働いていた時に、ジョン(仮名)が新卒で入ってきた。彼はアイビーリーグの博士課程を修了した優秀なデータサイエンティストだ。しかし、可哀そうなことに就職がちょうどコロナ禍と重なってしまった。初めは保険会社のデータサイエンティストを目指していたらしい。しかし、就職先がぜんぜん見つからず、全く分野の違う製薬企業に流れてきた。薬学、化学、生物学は素人だが、数値データ解析のプロだ。そういう彼は、理想的には、たくさんの同僚がいる大企業に入ってバックグランドをしっかり習得して切磋琢磨した方がよい。しかし、それもままならず、残った就職先が僕のいたスタートアップだった。仕方なしに?スタートアップに入ったのだ。しかも当初はテンポラリー雇用という不安定なポジションだった。しかし、ジョンはどんどん知識・経験を積み重ね、すぐに薬物動態のデータ分析の面白さに没頭するようになった。雇用形態もテンポラリーから正規雇用になった。スタートアップで1年ほど経験を積み、さあ、これからジョンがさらに羽ばたくぞ!と期待していた矢先だった。スタートアップの不安定さが、またも彼に試練を与えた。会社の最大のプロジェクトがとん挫し、社員の半数をレイオフすることとなった。ジョンもレイオフ犠牲者のひとりとなった。しかし、ここから挽回できるのが、日本と異なるところだ。レイオフから1か月も経たないうちに、ジョンは今度は製薬大手のポジションを得ることができた。スタートアップで1年間積み上げた知識・経験が実績となり今度は大企業がジョンを喜んで採用したのだ。結局、レイオフはジョンにとってキャリアアップに繋がった。若くしてスタートアップと大企業を経験し、今後ますますジョンはキャリアアップしていくことだろう。
ジョブ型雇用のアメリカ。労働市場の流動性が高いため、いつレイオフに会ってもおかしくない。そういう意味では不安定で残酷だ。ただし、そうなっても転職やスキルアップによる巻き返しが可能でもある。誰に対しても公平などと言うことは一切ない。でも、やり直すチャンスはある。一方、雇用を何とか守ろうとする日本。雇用した社員にはとても温かい。しかし、そこに入れないと生涯にわたって苦しむ。挽回ができないという構造的な問題。どちらが残酷で厳しい社会なのかを比べるのは本当に難しい。
2005年、僕は日本の製薬会社から出向の立場でアメリカに来ていた。ずっとアメリカに残りたくて別のポジションを見つけ、転職した。アメリカで働くという自分の夢を優先した。夢を叶えてくれた日本の会社と上司・先輩・同僚を裏切った。それから5年後、アメリカで転職で苦しんだことがあった。2010年、リーマンショック後の雇用減退期がまだ続いていた時だった。前職を辞めてから、6か月間失業期間が続いた。アメリカに来るという夢を叶えてくれた会社を裏切った罰が当たったのかもしれない。そんな時、その日本の会社の先輩から連絡をもらった。「日本に戻ってこないか?」
涙が出そうになった。裏切った自分をまだ心配してくれる。ただプロジェクトを遂行する場を与えるだけの会社ではない。繋がりを大切にする温かい日本人の会社。声をかけてもらって本当に嬉しかったことを伝えた上で、返事した。
「僕にとって社会に出て初めて入った会社。ゼロから育ててもらった会社。夢を叶えてもらった会社。その上で裏切って決別した会社。別の会社に転職するのと、この会社に戻って働くことは自分にとって訳が違います。じっくり考えさせてください。」のようなことを伝えた。
結局その後、アメリカで転職先を見つけ、日本の会社に戻ることはなかった。しかし、つくづく日本の会社のアメリカの会社にはない温かさ、日本人ならではの繋がりを痛感した。単に「世界の流れだから。アメリカのようにメンバーシップ型からジョブ型雇用に速やかに移行しろ。」とは、言えない。アメリカには、それよりはるかに残酷な教育格差、キャリア格差、経済格差が存在する。しかし、いくらうちわに優しくても、いったんそこに入れないものは生涯挽回する機会も与えられない日本の社会は、何とかしなければならない。輪を大切にする日本人だから、繋がりを大切にする日本人だから、視野を広く持つマインドセットを持てば改善できるところはいっぱいあるはずだ。そして、僕も本当にささやかながらでも問題提起していきたい。

