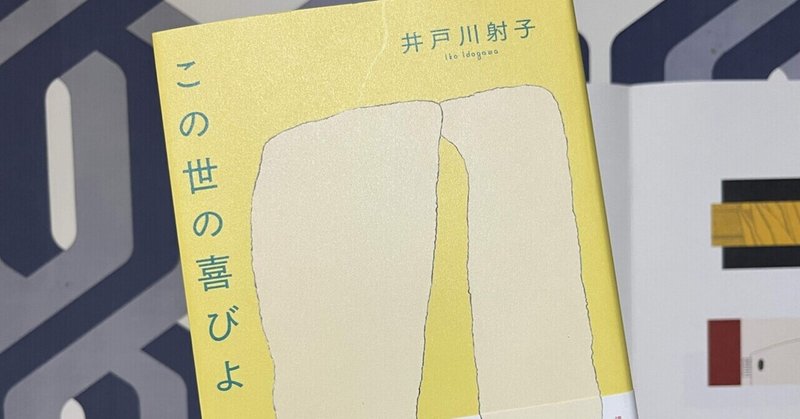
別の場所の、同じ記憶から ー井戸川射子『この世の喜びよ』
大学時代から映画や小説を勧め合う友人がいる。その友人とは頻繁に会うわけではないが、LINEで「あれ見た?衝撃だったよ」と伝え合う。最近ではぼくは『夜明けのすべて』を勧めて、友人からは『哀れなるものたち』を勧められている。昔からそういえば、友人は狂気と優しさが同居したエマ・ストーンが好きだった。
その友人に勧められて、井戸川射子さんの小説『この世の喜びよ』を読んだ。
この小説は、あらゆる「場所」を作る人に読んでほしい小説だ。とりわけ、ショッピングモールやフードコートの開発・運営に携わっている人、そのユーザーにはぜひ読んでほしい。どこにでもありそうな場所を巡る記憶が、こんなにも愛と尊厳に満ちたものになり得る。
病院、二つの記憶
井戸川さんは、『霞の入江』というエッセイのなかで、場所の記憶について書いている。
井戸川さんのおじいさんが入院されていた病院の描写が出てくる。
病室からの帰りは、パジャマを着ているのでもない私がエレベーターに乗るのも悪いし、見舞いの後はさっきまで堪えていた涙が出てくるしで階段で降りた、その先は祖父におやつを買ってもらった売店です。
この小さな一文に触れただけで、ぼくのなかに二つの病院の記憶が蘇った。
一つは、ぼくの祖父が入院していた病院に一人で見舞いに行った日のことだ。亡くなる数日前の、もう意識も朦朧としていて声も出ず、白濁した眼球をこちらにむけた祖父に手を握られ、ズボンの上に手を持っていった。オムツがぶよぶよに膨らんでいた。看護師の方に声をかけて、オムツを替えてもらうようお願いした。
おもちゃを買ってくれたり、彫刻刀の使い方を教えてくれたり、MP3プレイヤーを買ってもらったりした祖父が、朦朧とした意識のなかでも生きようとしている。祖父と話がしたかったし、何か声をかけて欲しかったが、オムツを替えてもらった祖父は疲れたのか、眠ってしまった。それが祖父との最後の記憶だ。
もう一つは、その前年の春、アフリカのケニアに旅行に行った学生時代のぼくが、日本に帰国してからマラリアが発症し、病院に入院したときのことだ。熱痙攣でどうしようもなくなったとき、祖父が車をだして病院につれていってくれた。順天堂病院では治療ができないとのことで、駒込病院まで祖父の運転でいき、そこで隔離病室に搬送されながらマラリアの治療薬の説明を受けた。熱痙攣で記憶はさだかではない。
入院は2週間ほどだった記憶がある。退院する2日前、熱は下がり、状態回復を待っていたぼくを、先ほど書いた友人がお見舞いに来てくれた。熱と嘔吐と血便とでゾンビのようになったぼくをみて「顔、紫色じゃん」といわれたことを思い出す。
さきほどの、井戸川さんのたった一文だけで、こんなにも記憶が想起される。井戸川さんのおじいさんが入院していた病院と、ぼくや祖父が入院していた病院はたぶん違うはずなのに、「病院」という場所の記憶をいやおうなく喚起する。
井戸川さんの文章は、読み手の内蔵に直接、それでいて優しく触れる。ヒリヒリとした感情の身体記憶と共に、そこに描かれた「場所」と自分の記憶を結びつけ、イメージを創造させる。
「あなた」になって、思い出す焦燥と愛着の記憶
『この世の喜びよ』は、とあるショッピングセンターが舞台になっている。そのなかにある小さな喪服店に勤める穂賀さんが主人公だ。フードコートにいる中学生の少女、ゲームセンターのヘビーユーザーのお爺さん、定員のお兄さんなどが登場する。
最大の特徴は、「あなたは」という文章で語られることだ。読者であるぼくは「あなたは」という呼びかけによって「穂賀さん」にさせられる。
いいの、捨てていいの、子どもが小さい時からね、床を拭いてそのまま捨ててもいいようなタオルを、いつも鞄に入れてるの、とあなたは答える。(中略)上の娘が一度、おもちゃ売り場でおしっこを漏らしてしまった時、あなたはとっさに下の娘のよだれ掛けをはぎ取りそれで拭いた。床に落とされたよだれ掛けは、首もとに収まっている時よりも薄く見え、もちろん先によだれで濡れていたので、吸い込めなかった分が床で光っていた。靴でもみ消すようにすると広がるだけだった、あの失敗と反省が、あなたに小さなタオルを持ち運ばせ続ける。
このような文章によって、ぼくは「穂賀さん」になりながら、「穂賀さん」の記憶を想い出し、それと同時に、自分の子育ての記憶、下の息子のよだれかけがびちょびちょで、上の娘がまだオムツをしていたころのコロナ禍のショッピングモールを、わけもなくウロウロしていたことを思い出す。と同時に、今も日々、用もなくショッピングモールのなかを慌ただしく子どもたちと歩く日々を過ごしていることをヒリヒリと思い知る。
「穂賀さん」の娘たちは、今は大学生と社会人1年目だ。だから、幼少期の子育てを穂賀さんは懐かしんで思い出している。焦燥と失敗の記憶として今も生々しく覚えている。だから穂賀さんは今も小さなタオルを持ち歩いている。しかし、同時に愛おしい記憶としても想起されているように読める。ショッピングモールでのお漏らしという、子育てをしていれば誰にでもあるような焦燥の場面のなかで、小さな失敗をしてしまったことをほろ苦く後悔しながらも、その頃の自分の尊厳を小さく讃えているようにも感じる。
ぼくは今まさに小さな子どもたちの子育てをしていて、毎日子どもたちの顔を見て、可愛いと思うこともあるが、もうほんとにいい加減にしてくれと嘆きたくなることの方が多い。保育園に送り出してから仕事を始める前にはもう本当にへとへとになっているし、保育園から帰って寝かしつけるまでの数時間は途方もなく感じる。眠った後に仕事を片付ける時、ぼくはボロボロになっている。そんな自分に尊厳を感じられない日々が続く。
「穂賀さん」になって育児を懐かしむ時、このボロボロになっている自分にも尊厳があり、その記憶にもいつか愛着が生まれること、だが同時にそれはほろ苦い記憶であり続けることを、予告されたような気持ちになった。そしてこのショッピングモールという場所は、自分にとって愛着と尊厳と同時に、焦燥、失敗、反省の色を帯びた場所になるのだということがわかった。
別々の場所の、共通の記憶を共に想起すること
井戸川さんの文章が、なぜこんなにも記憶を想起させるのか。それは彼女の出自が詩人であることにも由来している。『この世の喜びよ』は97ページの詩であった。言葉の選ばれ方、組み合わせられ方が、小説というよりは詩のようで、一言一句が内蔵に触れるように感覚を呼び起こす。
それゆえに、小説に描かれた架空の場所であっても、読み手の数だけ別々の場所が想起される。この本を読んだ人と、場所の記憶について話してみたいし、同じショッピングモールで子育てをする人にも読んでほしい。
この小説からぼくが学んだことは、「人は、別々の場所をめぐる、共通の記憶を見ることができる」ということだ。そしてそれと同時に、それがそのときは失敗や反省の記憶であったとしても、愛着と尊厳を見出すことができるということだ。
ぼくがもしショッピングモールの開発に携わるなら、共に開発する人とこの小説を読み合わせ、対話するところからどんなショッピングモールをつくるかを話したい。いや、たとえ図書館や美術館であっても、場所をつくるときはこの小説に立ち返り、可能なら関係者と共に読み合って、別々の場所でありながら共通する記憶を手繰り寄せたうえで、「場所をつくり、営む意味」を考えたい。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。いただいたサポートは、赤ちゃんの発達や子育てについてのリサーチのための費用に使わせていただきます。

