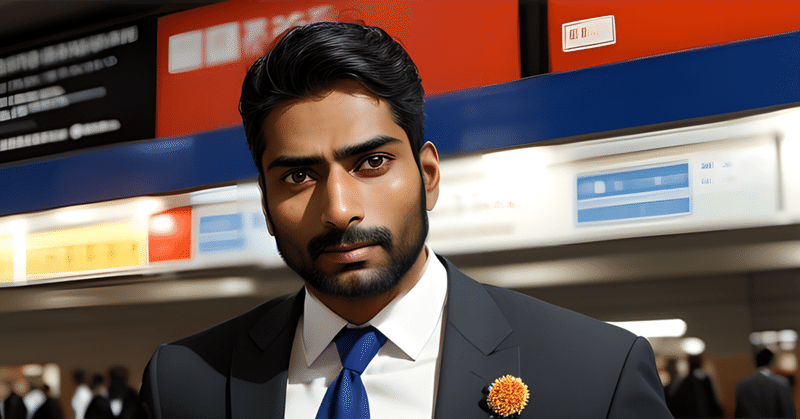
人手不足対策の外国人雇用に必要なのは言語対応よりも働きたくなる労働環境つくり
「外国人=言語対応」が脊髄反射になっていないか
日本はおもてなしの国だ。日本に来た外国人が嫌な思いをしないようにと細かいところまで気を遣っている。非英語圏の先進国に旅行に行くと思っていたよりも英語が通じなくて困ったという経験を持つ人は多いだろう。日本も店員の英語力には難があっても、外国人観光客が訪れるようなところは複数言語での説明書きや写真メニューなどが準備されるようになった。外国人観光客に対してはこれで良いだろう。しかし、日本で働く労働者に対しても同じ対応で良いのだろうか。
2000年代に楽天をはじめとして社内公用語を英語にすると脱日本語を目指した企業がいくつもあった。しかし、アメリカに本社を置く世界最大クラスのブランディングファームのインターブランドジャパンが発表する『Best Japan Brands 2023』のTOP5では、ルノーとアライアンスを組む日産を除いて、社内公用語は日本語の企業(トヨタ、ホンダ、ソニー、任天堂)だ。
当然、グローバル企業で働く社員には多言語能力が求められる。それは業務上必要だからだ。しかし、「外国籍人材を雇うのだから、言語対応」と安易に考えすぎてはいないだろうか。
2種類の外国籍人材
外国籍人材を増やそうという動機は、従来は事業のグローバル化が背景にあった。海外で事業展開をするのだから、現地の従業員を雇用する必要があり、本社で管理・監督するポジションにも外国籍人材が必要になった。しかし、昨今の流行には従来とは異なる背景が2つある。
1つは、国内で調達が難しい高度な専門性を有した人材の獲得競争だ。ITエンジニアが代表的だが、高度な専門性を有した人材の不足は世界的なトレンドだ。その獲得競争は戦争に例えられるほど激しくなり、国や地域を問わずに世界中の企業が狙っている。
もう1つは、国内の人手不足問題の解消だ。リクルートワークス研究所が『労働供給制約社会』と呼ぶように、少子高齢化と人口減少によって、社会活動を維持するための労働人口が国内だけでは賄えなくなる。その対策として、外国人人材の雇用を促進しようというものだ。現在は技能実習生制度がこの目的で使われ、本来の目的である人材育成とは異なるとして問題視もされている。
言語対応よりも大切なこと
外国籍人材を採用する目的として、高度な専門性を有した人材を国際的な労働市場から得ようと考えると言語対応は必須だ。人材獲得の競合が諸外国となるため、より良い条件を提示できなければ人材から選んでもらうことができない。
一方で、人手不足を補填するときには、言語対応をどこまでやるのかは議論の余地がある。人手不足でただでさえ業務負担が大きくなっている現場に対して、言語対応で更なる負荷をかけることは現実的ではない。それよりは、日本語教育を充実させて、日本で働く外国籍社員の言語力を高めるという選択肢もある。
もともと、日本語は外国人にとって人気のある言語だ。外国語学習アプリのDuolingoによると、日本語は世界で5番目に人気の言語であり、アジア圏では最も人気があるという。国際交流基金の調査でも、日本語教育を実施している国・地域は141か国・地域(2021年)であり、コロナ前の2018年の142カ国・地域より1か国減少しているものの、基本的には増加傾向にあると言える。日本語学習者数は2012年の398万人がピークではあるものの、2021年は379万人で、過去42年間で学習者数は29.8倍に増えている。
また、外国籍人材を採用したとしても、日本企業での働き方に適応し、パフォーマンスを発揮してもらえるかどうかは別問題だ。そもそも、日本人同士でも、中途採用者の定着に課題感を持つ企業は数多い。それなのに、外国籍人材の定着となると、更にハードルがあがる。
外国籍人材にとって、日本での働き方でリスクとして捉えられやすい課題が3つある。
1つ目は、昇進スピードの遅さと基準の不明確さだ。世界で主流となっているジョブ型では、ポストに空きがでたときに、そのポストの要件に見合った能力や経験があるのならば応募して、認められたら昇進する。つまり、昇進するかどうかは個人が決める。日本は会社側で昇進・昇格をコントロールしようとするので、どうしても個人の自由意志と比べるとスピード感に欠けるし、意思決定のロジックも不透明になる。
2つ目は、キャリアを自分で作りにくいことだ。1つ目とも被る部分があるが、日本では社員がどのような仕事に従事するのかについて、会社側でコントロールすることを好む傾向にある。このことが、外国籍人材にとって、キャリアを開発していくうえでリスクがあると捉えられてしまう。
3つ目は、給与の上がり幅が小さいことだ。以前から、日本企業の管理職の給与は欧米企業と比べて低い傾向にあった。それでも、企業内の重要なポジションのほとんどを日本人で占めていたときには大きな問題にはならなかった。しかし、2010年代からグローバル化によって、管理職以上に外国籍人材が増え始めると問題視されるようになってくる。例えば、このような記事が2016年の時点で紹介されている。
英人材紹介会社ヘイズの調べでは、製薬業界の研究開発部長職で、中国と香港は年収4000万―5000万円台に対し、日本は3000万円にとどまった。JACの調べでは、シンガポールにおける外資系企業の経理部長職の年収は15万シンガポールドル(約1245万円)に対し、日系企業は12万シンガポールドル(約990万円)と2割低かった。同じ職種でインドネシアでは他の外資系企業と比べ、日系企業の年収は3割低かった。
2021年には、日本の大企業の管理職の給与が、タイやフィリピンの管理職の給与よりも低いことが、ダイヤモンドオンラインの記事で取り上げられていた。日本企業の給与は諸外国と比べて上がらない。
加えて、OECDの平均年収ランキング(2022年)では、日本は30カ国中21位で韓国にも追い抜かれてしまった。G7で日本より低いのはイタリアのみだ。
このような状況で、日本企業で働き、キャリアを築いていきたいと考える外国籍人材はどれほどいるのだろうか。まだ、日本という国に魅力を感じ、多くの外国人が日本語を学んでくれている現状があるうちに、外国籍人材にとって魅力的な労働環境を整備することが求められる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

