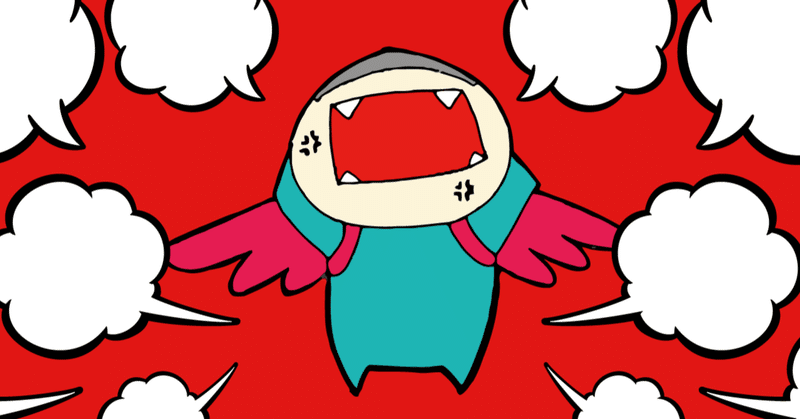
当事者研究の「反転の問い」の魅力
最近、仕事を終えると疲れから、育児家事の時間にイライラしてしまうことが多いのです。17時に仕事を切り上げ、保育園に迎えに行き、疲れ果てた子ども(4歳と2歳)を歩いて連れて帰り、お風呂と食事の準備をしながらパートナーの帰りを待ち、みんなでご飯を食べて寝る。文字にすればそれだけのことが、本当にハードです。
子どもたちも疲れているので、不平不満のオンパレードです。ラーメンが食べたいというので作ったら「ラーメンじゃなくてうどんがよかった」みたいなこと言われるのはしょっちゅうですし、飲んでた豆乳を床にぶちまけたり、お箸でお肉が掴めないと叫んだり…。
「いい加減にしなさい!」と叫びたくなるけどグッと我慢していますが、情けないことについ舌打ちしたり「ああもう!」と声を漏らしたりしてしまいます。
そんな苦労を、どうやって乗り越えたらいいんだと、最近「当事者研究」という方法を調べています。当事者研究は、統合失調症や依存症などを当事者が乗り越えるために生まれた方法です。
当事者研究は、統合失調症や依存症などの精神障害を持ちながら暮らす中で見出した生きづらさや体験(いわゆる“問題”や苦労、成功体験)を持ち寄り、それを研究テーマとして再構成し、背景にある事がらや経験、意味等を見極め、自分らしいユニークな発想で、仲間や関係者と一緒になってその人に合った“自分の助け方”や理解を見出していこうとする研究活動としてはじまりました。
自分自身の苦労のパターンを描き出し、そのパターンがいつ頃からはじまったものなのか、そのパターンの中で何が起きているのか、自分のことを他人事のように眺めながら、みんなであれこれと対話していく手法だと、ぼくは解釈しています。
とりわけ特徴的なのは、「いい苦労をしてるね」「もう少し、苦労を増やした方がいい」「行き詰り方が上手」など、苦労や行き詰まりというものへの捉え方を反転させたユーモアの視点です。
「苦労しないためにどうすればいいか」をすぐに考え始めるのではなく「どのように苦労しているのか」「その苦労によって得ているものは何か」「どうすればいい苦労ができるのか」を考え、苦労をいわば味わい尽くすように研究をしているように見えます。
育児や家事は依存症や精神疾患とはことなりますが、苦労の連続です。「育児をもっと楽にする方法」「無理しない育児」といったキーワードはよく見かけますが「育児でもっといい苦労をするために」「育児の上手な行き詰まり方」と言った捉え方で、育児の苦労を味わい尽くすこともできるかもしれません。
ぼくで言えば、すぐにイライラしてしまうので、それを「イライラ悪魔」に取り憑かれことにしてキャラクターにしてみるのも面白いかもしれません。そのうえで、「イライラ悪魔のいい側面は?」「最高のイライラ悪魔に取り憑かれる方法とは?」といった反転した問いを考えていくと、日々の苦労が何か別のものに変わっていきそうな予感がします。
そしてそれはなんだか、とても魅力的だと思うのです。育児の苦労を、無理にどうにかしようとするのではなく、味わい尽くしてみたいと今感じています。
文学研究者の横道さんは、当事者研究の方法から文学を創作されました。
育児や家事に苦労する一人一人にも、苦労の物語があるはずです。育児の苦労の当事者研究会を開き、そこから物語が生まれるような、そんな場があったらいいなぁと思っています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。いただいたサポートは、赤ちゃんの発達や子育てについてのリサーチのための費用に使わせていただきます。

