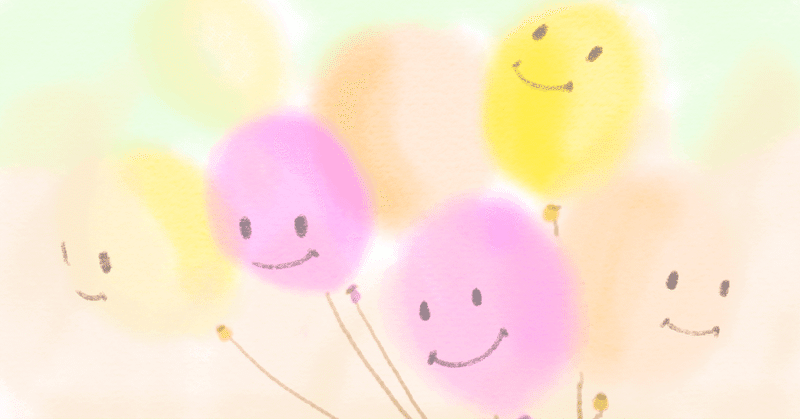
「計画された偶発性理論」(Planned Happenstance Theory)〜山登り型 vs 川下り型のいずれかを選ぶ必要は必ずしもなく、山あり谷ありでいいのかも
3ヶ月前に、自分のライフやキャリアは川下り型だと思うという記事を投稿しました。その後より深掘りしてみると、私のこれまでとこれからは必ずしも川下り型とも言い切れず、山登り型とミックスのハイブリット型だなと思うように至りました。どういうふうに説明づけられるのだろうと考察する中で、「計画された偶発性理論」(Planned Happenstance Theory)という考え方に出会い面白いなと思ったので、そのことについて綴りたいと思います。
「計画された偶発性理論」(Planned Happenstance Theory)とは
スタンフォード大学で教授を務めていたJohn D. Krumboltz氏が1999年に提唱した考え方です。山登り型を志向して目標を設定して歩もうとしても、多くの場合は思い通りにならない。けれど、その過程で起こる想定外の出来事が、後にポジティブな結果に結びつくことが多々ある。偶然が起きたときにそれをうまくチャンスに転じさせることができるか、そのための術を磨くことがこれからの時代に求められる…そんな考え方です。
リンク先の日経新聞記事では、元TOTO社長の木瀬照雄氏、アートコーポレーション名誉会長寺田千代乃氏、ノーベル化学賞受賞者の吉野彰氏の具体例も挙げられています。
クランボルツ氏は、世の中で成功しているエグゼクティブは若いときからしっかり将来展望を描き、計画通りに希望のキャリアを積んできたに違いない…と仮説を立てました。そして、どんなキャリアプランを立てれば人は成功できるのかを探ろうと〝勝ち組〟と目される方々に聞き取り調査を始めます。ところが、仮説に反してほとんどの人は希望通りのキャリアを歩んでいませんでした。むしろ、成功要因の8割は想定外の出来事など偶然がもたらしていたと分かりました。そこから導き出した成功の秘訣が、綿密にキャリアプランを立てるより、想定外の偶然を味方にする術を身に付けよ――でした。
(中略)
「そうか! 成功の8割を偶然がもたらすなら、何も考えず、なすがままに行動すればよいのか」。こう受け止めた方もいらっしゃるかもしれませんが、「計画された偶発性理論」の肝はそこではありません。「Planned Happenstance」という原文の英語の方がクランボルツ氏の主張を的確に示しています。仕事で成功する要因の8割が偶然なら、その偶然を意図的に起こすか、偶然を計画的に利用しなさいと、クランボルツ氏は説きます。
机にしがみついていても偶然は向こうからやってきません。あちこち動き回れば偶然と出合う可能性は高まります。さらに想定外の出来事に出くわしても、その瞬間にそれを生かす準備を日ごろ怠っていれば何も起きません。吉野氏の事例でいえば、10年間素材に関する研究に努めていたからこそ、専門誌をヒントに頭の中の知見が結晶化したのです。
山登り型 x 川下り型 = ハイブリッド型のように思える歩み方
「計画された偶発性理論」(Planned Happenstance Theory)の定義をこうして眺めていると、まさに3ヶ月前の投稿で説明した山登り型と川下り型をマッシュアップしたハイブリッド型な考え方のように思えます。
私自身のこれまでに照らしてみると…高校時代必死にTOEFLなどの受験を重ね卒業後はカナダに留学する予定でしたが(山登り型)、父の勧めもあり半年限りのつもりで国内の大学に進学しました。そこで出会ったのが模擬国連/ Model United Nations。学生が国連の会議をシミュレーションするというサークル活動ですが、これにすっかりのめり込み急いで留学する理由が見当たらなくなってしまい、長い時間をかけて準備してきた留学を取り止める決断をしました(川下り型)。模擬国連との出会いという偶然を選択し、生かすことを決めたあの時の判断が、その後、国家公務員を志そうと思ったり、アフリカへの道を切り開いてくれたり…今につながっているのだと思います。
歩みの中では、その時々に大なり小なり目標を立てることもある。その頂を目指して山を登っているうちにいろんな巡り合わせや出会いがあり、分岐点で選択をし、時に流されながら歩んでみる。意図を持って計画的に選ぶこともあれば、なんとなく直感的に選択することもあるので、必ずしも計画された偶発性を全うしているわけでは無い気もしますが、こうして見ると、私の今までもこれからも、山登り型 vs 川下り型のいずれかを選ぶ必要は必ずしもなく、山あり谷ありでいいのかもと思えるようになってきました。
先の予見できない時代に入ったからこそ、柔軟な考え方で切り開いていきたい
クランボルツ氏は新しいキャリア理論が必要になった背景に経済環境の変化を挙げます。産業構造の変化が緩やかな時代であれば、将来も読みやすく、長期的プランも容易に立てられました。ただ、変化が激しい状況ではそもそも今ある仕事や職種が10年後、20年後もあり続ける保証はありません。緻密に練り上げた計画ほど軌道修正が難しく、時代の変化に順応できません。彼が「計画された偶発性理論」を提唱したのは20年以上前のこと。変化の速度は増しており、その有効性はさらに高まっているように思えます。
ChatGPTの普及に伴って、これまでなんとなく知識として頭の中にあったシンギュラリティやAIが人間を凌駕する世界が現実味を帯びてきたような気がします。私の仕事も含め、世の中の多くの仕事が10年ごと言わず数年後、数ヶ月後にAIに置き換わっていくことも起こりえるだろうなと感じます。
そう考えると不安で眠れなくなりそうですが、思い描いた道をそのまま歩めそうに無いのであれば、偶然を引き寄せる行動を取ってみよう、そこから何が生まれるか模索してみよう…と考え動いた方が、きっと何かしらの道が開けるはず。
山登り型だけが、川下り型だけが解じゃ無い、混ぜこぜの歩み方を自分に認め許容しながら、しなやかに選択を重ねていけるようになれたらいいなと、3ヶ月前より少し柔軟に考えられるようになりそうです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

