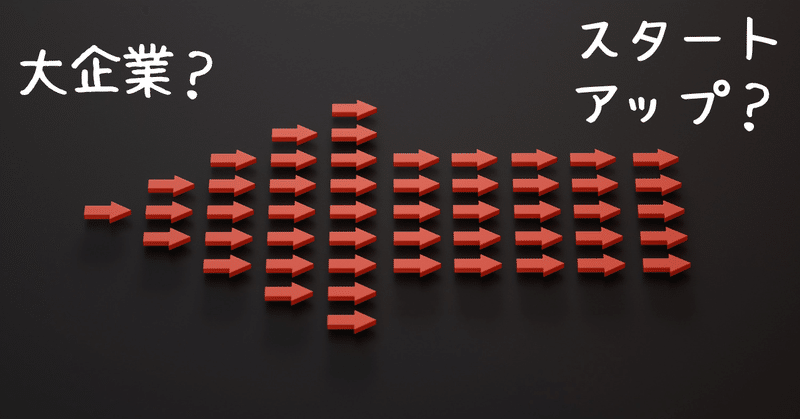
スタートアップに人材がどんどん流入する社会にしていこう!
今年から、スタートアップ推進に政府が本腰を入れています。
スタートアップを推進する上での大きな課題の一つとして「スタートアップでの優秀な人材の確保」があります。成長著しい新興企業ではリソース不足はつきものですが、中でも人材というリソースの確保については、あらゆるスタートアップが頭を悩ませていると言っても過言ではありません。
そこで今日は、大企業などスタートアップ外にいる人材をいかにしてスタートアップに流入させるかということについて、考えてゆきたいと思います。
動き出す官民の様々なプレイヤーたち
まず前提として、スタートアップを推進していくための日本における大きな動きについておさらいしておきます。
■政府の動き
まず、岸田首相の年頭記者会見で、成長戦略の柱として発表されました。ここから「これからはスタートアップだ」という機運が加速しました。
(それについて年始にまとめた記事👇)
最近でも、5/5にイギリスでの岸田首相のスピーチの中では、新しい資本主義を構成する4つの柱の一つとしてスタートアップが掲げられています。
■民間の動き
そうした中、3/15には経団連からも38項目の施策が提言されました。
網羅的で実践的な内容がまとまっており、今年政府が発表予定の「スタートアップ推進5ヶ年計画」にも大きく影響するのではないかと思われます。
経団連副会長の南場智子さんから発表もされ話題になっていたので、記憶のある方も多いのではないでしょうか。
■官民連携した動き
産官学が連携してエコシステムを形成し、スタートアップを推進していくという流れも生まれています。具体的には、「一般社団法人スタートアップエコシステム協会」が立ちあがり、3/29に発表されています。
僕も、スタートアップエコシステム協会では設立時の賛同者の一人として、このエコシステムそのものがスタートアップ的な組織カルチャーになるように微力ながら力になれればと思っています。
そして、政府・民間に限らず、上記にいずれの場においても、必ず課題として挙げられるのが人材の確保なのです。
既にスタートしている行政の支援事業
スタートアップの人材確保という課題を解決するため、人材流動性を向上させるための実証事業が昨年動いていたのをご存知でしょうか?
経済産業省の「スタートアップ向け経営人材支援事業」としてのSHIFT(x)です。
公募に応募した中から、7つのコンソーシアムが認定され、政府からの補助金を受けながら、実証を進めています。
僕も公募の審査委員として参加させていただき、各コンソーシアムからの提案や、その後の進捗などをお伺いする機会に恵まれました。
各コンソーシアムの取組みとしては、スタートアップの採用支援、副業やプロボノを通じたスタートアップ体験、個人の意思決定支援のコーチングなど、多岐にわたる事業が並んでいます。
なお、補助金事業としては、日本がこれから世界で勝ち得る領域として、ディープテックなどの領域の支援がより優先されるようになっています。
最終成果の報告はこれからですが、実証事業を併走して見てきた自分の感想としては、「大企業からスタートアップへの流動の難易度は極めて高い」というものでした。その理由は多岐に渡ります。
スタートアップから見て即戦力と言える人材になかなかマッチしない
給与が減るケースがあり、候補者がなかなか踏み切れない
ディープテックなど時間がかかる事業の成功を候補者が確信しきれない
大企業を辞めることへの家族の同意を候補者が得られない
・・・など。これらはほんの一例ですが、こういったことが相まって、実証事業を行う半年強という短期間では、大企業からスタートアップに飛び込むケースを急激に増やすことは難しい状況でした。
スタートアップに人材が流入するには?
そうした状況を踏まえ、スタートアップに大企業の人材を流入させるには、スタートアップ側の採用活動の強化や、人材紹介会社の積極的な活動だけでは難しく、もっと構造的・長期的に腰を据えて取組む必要があると思います。
そのために企業や個人が取組むべきこととして、以下3点を僕なりの視点からお伝えしたいと思います。
(1) メガベンチャーを経由する
社員数万人の大企業の人材が、いきなり社員数名のスタートアップに飛び込むのは、採用される側・する側の双方にとって意思決定の難易度が高すぎると思います。
大企業では、どんなに優秀であっても、全社的な経営を若いうちから経験できる機会は少なく、縦割りの中の決められた範囲の仕事だけをやることがほとんどです。
そこから、いきなり全社的な経営を考える立場になることも難しいですが、部門とか役割とか関係なくなんでもやらないといけないのが数名のフェーズです。その環境を具体的に想像し、理解し、自分の動き方を変え、パフォームする、ということを即座にできるかというと、とても難しいですよね。
これは、本人も辛いわけですが、受け入れるスタートアップ側としても、業務を限定するような動きをされていたら耐えられないわけです。
結果として、互いに働くイメージが湧かずに転職の意思決定がしきれない、ということになります。
これの対策としては、メガベンチャーと言われるような、社員数百名から数千名の元スタートアップへと一度転職することです。
このフェーズのスタートアップであれば、「仕組み化したい」「スケールしたい」という組織的なニーズが強く、大企業での経験を一定活かせます。
その上で、スタートアップのような柔軟でスピーディーな動き方だったり、一人ひとりが自ら考え意思決定するといったカルチャーにも触れることができます。
このようにして、スタートアップカルチャーに触れつつも、自分の強みが活かせるような、そういう組織に一度身を置いて、2−3年ほどの経験をすれば、その次にもっと小さなスタートアップに行きやすくなるのではないでしょうか?
特に、メガベンチャーにいくと、「数人の頃はね」という歴史を聞く機会がすごく多くて、そしてそのフェーズをみんなすごく楽しそうに話すんです。そうやって、数人のフェーズがどういう世界かを経験者から学び、自分の中での解像度を上げてから、移ることができると思います。
僕自身、マクドナルドという大企業を離れた際に、当時500名ほどだったメルカリに移りましたが、一定組織だってきたタイミングで、しっかり組織化を推進したいフェーズだからこそ、自分が貢献できる領域がありそうな気がして、勇気を持って転職する決意ができたという感覚がありました。
(2) 個人のリスキリング
メガベンチャーに行くにせよ、スタートアップに行くにせよ、キャリアのジャンプをすることには変わりありません。
従来とは全く異なるタイプの人と働き、異なる事業に携わり、異なる職種の仕事もすることになります。新しいことばかり。
そうした環境に飛び込むためには、全くのゼロから飛び込むよりは、ベースとなる知識や経験を何かしらの形で補っておくことが有効です。
先のShift(x)でも、副業やプロボノの形で、大企業で勤めながらスタートアップの経験を積む機会を醸成する事業がありました。
こうした経験を積んでおくことで、スタートアップのカルチャーがどういったものか体感し、自分に合うかどうかの判断がしやすくなります。また、副業で経験するうちに双方の信頼関係が高まり、そのまま転職するといったケースもあり得ます。
また、経営学修士(MBA)で学ぶというのも一つです。
僕が教員を務めているグロービス経営大学院では、昨年度1,000人を超える卒業生が巣立っていきました。実務を重視するグロービスでは、実際の企業のケーススタディを用いて、実践的に経営を学びます。
そして、「創造と変革の志士」の輩出を掲げ、スタートアップの経営者となって新規事業を創造するケースや、大企業のターンアラウンドなどの変革のケースに取り組みます。
MBAでなくてもいいのですが、このように経営の追体験をしておくことで、いざという時の引き出しを多く持っておくことはとても有効です。
僕自身の話でいうと、1社目のマクドナルドで働きながらグロービス経営大学院に学生として通いました。メルカリに転じる際には、そこで出会った仲間にメルカリを紹介してもらったことがきっかけになりましたし、メルカリに入ってからもスタートアップがどういうものか、周囲の人たちやケーススタディから一定の基礎知識・追体験をしておけたことは大きかったと思います。
また、マクドナルドではマーケティング職を経験しましたが、メルカリで人事や社長室の仕事を担えたのも、経営学の中で人材マネジメントだったり、ファイナンスといった基礎的な経営のフレームワークを認識していたので、最低限の共通言語を持って専門家と会話ができたことは、「学んでおいてよかった」と心から思った瞬間でした。
その後、兼業としてグロービス経営大学院で教壇にも立たせていただくようになり、人前で講師を務めたり、ファシリテーションをするというスキルも身につきました。このように副業から身につくものもたくさんあるということです。
(3) 企業における出戻りの推奨
最後の3点目は、出戻りの推奨です。最近「アルムナイ」と呼んで卒業生を組織化することが進んでいますが、これも卒業生をその後に自社に戻すなどして組織内で再度活用することを想定した動きと言えます。
従来の伝統的な日本企業においては、入社するタイミングは新卒しかなく、一度退職したら戻れないというのが一般的な考え方でした。
年功序列を前提とし、定年まで働くのが常識だったので、辞める人はある意味で裏切り者であり、年功序列のルールから逸脱する人だという考えです。
しかし、新卒一括採用で社内の育成だけに頼ると、どうしても知識や経験が社内のネットワークに偏ってしまい、組織に新しい力が加わることがありません。特に、既存市場がシュリンクする日本においては、成長市場での新規事業をスタートアップのように作っていく必要が出てきます。
昨今、ジョブ型雇用という言葉とともに、中途での専門家の採用が進んでいます。そうした人材が新規事業など新しい領域を担っています。
しかし、大企業が新規事業に取り組むのであれば、何らか既存事業や既存組織とのシナジーを求めます。だとしたら、組織内に精通した人材がいた方がいいですよね。
そこで、企業サイドとしては、優秀な若手がスタートアップやメガベンチャーに挑戦することを積極的に奨励するべきだと思うのです。そして、2−3年経験した後、主要なポストで戻すのです。社内のことも知っている、そしてスタートアップ的な動きもできる、そうした人材を育成することができます。
しかも、修行中の2-3年は、人件費もかからなければ、その間に失敗などして経験を積んできてくれるわけです。そうした失敗による自社のリスクはゼロで、リスクは修行先が負ってくれているとも言えます。
そうではなくて、一度出ても戻ってくる時に、その経験分を加味して戻せる。外部で経験して、レベルアップして帰ってくる。そういう人材を積極的に登用するべきです。
僕も、マクドナルドを退職する際に、当時社長のサラ・カサノバさんと1on1を何度かさせてもらってよく話をしました。
そこで彼女は、こう言ってくれたんです。
「あなたがマクドナルドで社長や経営職を担うようになるのであれば、マクドナルドの中で育つことも良いけど、外の経験をすることも良いともうわ。ちゃんと経営の経験を外で積んできたら、また戻して活躍してもらうから、いつでも連絡してきなさい。他社のお金使ってたくさん経験して失敗して、またマクドナルドで成果を上げて貢献してくれたら最高ね(笑)。」
最後の一文は笑い話程度に言ってましたが、確かに実際そうなんですよね。
そうした企業が増えていくことを願っていますし、デジタル庁はじめ公務員の世界もそうしていけたらなぁなんて思ったりもしています(もちろん、簡単ではありませんが)。
さいごに
言いたかったことは、産官学みんなで力を合わせ、スタートアップに挑戦しやすい社会を作っていこうということです!
日本って、誰かの強いリーダーシップよりも、社会の雰囲気が重視されるなぁとつくづく感じます。
みんなで雰囲気を醸成して、「スタートアップで働くのが普通」「子供の憧れの仕事はスタートアップ」なんていう世の中にしていけるといいですね。
経済産業省では、昨年のShift(x)に続いて、スタチャレ(スタートアップチャレンジ推進補助金)という事業もスタートしました。
仲介業者向けの公募など一部は終了していますが、人材を受け入れるスタートアップや人材を輩出する大企業などの募集はこれからです!
人材育成を考えている大企業の方、スタートアップで人材を探している方、スタートアップで働いてみようと考えている個人の方など、皆さんぜひこの事業にも関心を寄せていただき、今後の発信もお待ちいただければと思います〜!
こうした制度も活用し、皆でより良い社会を作ってゆきましょう〜!!
(2022/06/15追記)
コメントにて、「給与の問題があるのでは」とのご質問いただきまして、ありがとうございます!
僕なりに上場会社との給与面も含めた比較を以前に書いているので、そちらもよろしければ是非ご覧ください〜!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

